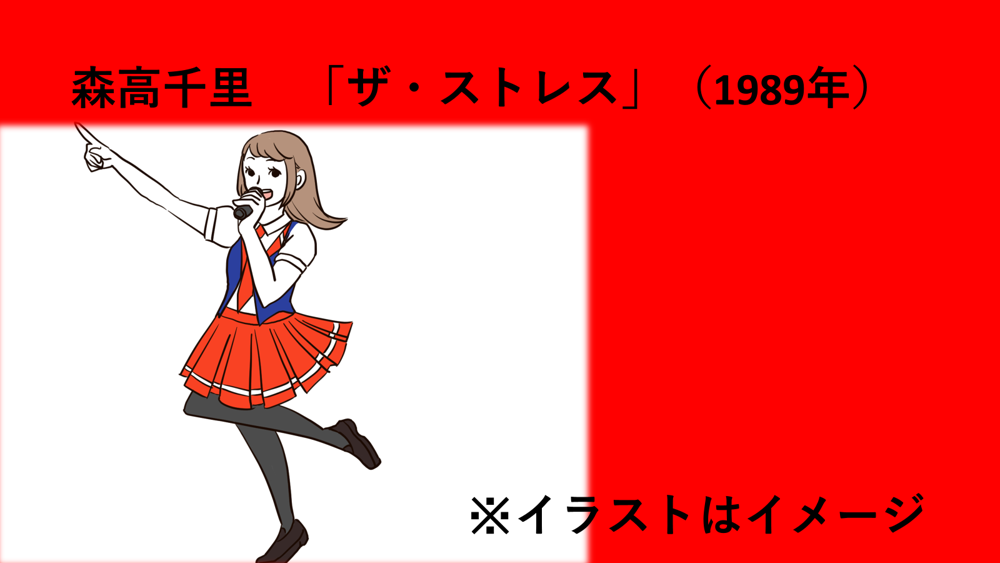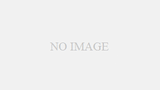現代は「ストレス社会」であると言われることを頻繁に耳にします。 昨今では、ストレスチェックが義務化されたように、ストレスに対する意識や 注目度はより高まっているかのような動きを感じます。 そもそも、ストレスという概念はどのようにして社会の中に登場してきたのでしょうか。
ストレス学説登場からの歴史的変遷
まず、世界的には、ハンス・セリエ博士の、「ストレス学説」(1936年)の提唱が大きな転機になることは確かだと思います。ストレスという用語は物理学の世界のもの でしたが以降、医学や生理学、心理学の世界に登場していくことになります。 今では、看護や心理学のテキストにセリエ博士の名前とその理論が登場することは当たり前のようになっています。
ストレス学説以外
- ホームズらによるライフイベント研究
- キャノン:危急反応を提唱(1915年辺り)。アドレナリンと関連を示す。
- ベルナール:実験医学的研究法
その後、いかに日本社会の中にストレスという表現がこれほどまでに定着するように なったのか、そのいきさつを明らかにするにはなかなか困難なものがあります。 (学術的な動向という事であれば、論文を過去に遡っていけば良いわけですが、 言語についてはまた別な手法も必要になるかと思います。)
森高千里
一説には、森高千里さんの「ザ・ストレス」(1989)という歌がそのきっかけになった とするものもあります。
災害
推測になりますが、我々の視点からすると、北海道南西沖地震(1993)をはじめと する大災害が一つの契機になっているようにも見えます。
心療内科の標榜
また、心療内科という診療科目は1996年から外部標榜が認められています。 心療内科医の先生方がストレスという言葉を用いたことも一つの 契機と言えないでしょうか。(因みに臨床心理士の登場は1988年の事です) 列挙してみると、1980年代後半から1990年代中盤にかけて何かが動いている ように見受けられます。
法制化や国家的なストレス調査
ストレスに関する、大規模調査や法制化も徐々に進んできました。 これらは、主に、労働の分野で整備されてきました。 (労働安全衛生法という法律には、1972年当初、メンタルヘルス関連の 内容は含まれていなかったようです。)
例えば、厚生労働省は、1982年から労働者健康状況調査を5年ごとに 調査しています。この調査内容を見ると、ストレスに関する内容が含まれています。 この調査によると、5割、6割位の人が、強いストレスを感じている結果が示されました。 そして、昨今では、ストレスチェックが義務化されました。 その他、各自治体が行う調査にも、ストレスと関連する項目が含まれる ようになってきています。
まとめの年表
ここまでのことを年表形式にしました。
- 1936年 ハンス・セリエがストレス学説を提唱
- 1945年 終戦
- 1982年 厚生労働省が労働者健康状況調査を開始
- 1988年 臨床心理士資格開始
- 1989年 森高千里 「ザ・ストレス」を発表
- 1986年 心療内科の外部標榜が認められる
- 1993年 北海道南西沖地震
- 1995年 阪神・淡路大震災
- 2002年 日本ストレスマネジメント学会発足
- 2011年 東日本大震災
- 2015年 ストレスチェックの義務化